序章:閉ざされた鉱山の奥で
久慈市の外れにある旧鉱山跡。
戦後の高度成長期に栄え、いまはフェンスに囲まれた廃坑道。
地元では、こう呼ばれている。
「鏡坑道(かがみこうどう)」――覗くと、もう一人の自分が動く場所。
坑内の奥には、鉱石の壁が一面だけ異様に滑らかで、
まるで鏡のように光を反射する石層があるという。
昼でも暗い坑道の中、
その壁だけが淡い青白い光を放っている。
だが、問題はそこを「見る」ことだ。
そこに映るのは、あなたではない。
“もう一人のあなた”なのだ。
第一章:久慈という“掘りの街”
1.1 鉱山の記憶
久慈市は、古くから琥珀(こはく)と鉄鉱の採掘で栄えた。
「久慈琥珀」は日本最古級の産出地であり、
国の天然記念物にも指定されている。
琥珀は数千万年前の樹脂の化石で、
古代から“魂を閉じ込める石”として珍重されてきた。
鉱夫たちはそれを「光の墓」と呼び、
掘り出すたびに、何かの声が混じると言って恐れた。
久慈市立図書館に残る郷土誌『久慈鉱山記』(1964)には、
こうした記述がある。
「坑道奥の岩壁に、鏡のごとき鉱層あり。
夜勤の者、己が影を見て声を失う。」
その頁は、そこだけ黒く煤けていた。
1.2 鏡の鉱層
地質学的には、坑道内で発見された“鏡層”は
黒曜質石英脈(こくようしつせきえいみゃく)と呼ばれる現象に近い。
ただし、報告書にはこうもある。
「光の反射が異常。
照明を消しても微光を発する。」
つまり、外光のない地下で、
何かが自ら光を放っている。
鉱山関係者の証言では、
その光は“まるで呼吸しているように”明滅するという。
第二章:坑道の噂
2.1 鉱夫の失踪
1960年代、坑道作業員のひとりが夜勤中に行方不明になった。
仲間によれば、彼は「鏡の壁を撮りたい」と言い残して坑内に入ったという。
翌朝、見つかったのはカメラだけ。
フィルムには、何も写っていなかった。
……いや、正確には、“逆さの坑道”が写っていた。
天井に地面、地面に天井。
そこに、上下逆さの人影が立っていた。
2.2 覗くと“反転する”
坑内の案内を一時的に引き受けていた元鉱員の話。
「あの壁は鏡みたいだけど、自分は映らないんだ。
代わりに、少し遅れて“別の動き”が見える。
それが笑ったり、こっちを向いたりする。
……で、目を合わせたら終わりさ。」
彼は、以後一切その場所の話をしなくなった。
インタビュー翌月、彼は姿を消した。
自宅には、鏡をすべて裏返した状態で残していたという。
2.3 “逆になる”現象
体験者の証言によれば、鏡坑道で起きる異変には三段階ある。
- 反射の遅れ:映像が自分より0.5秒遅れて動く。
- 視線の反転:映像の“自分”が逆の方向を見る。
- 入れ替わり:視界が急に反転し、以後、世界が“裏返る”。
第3段階を経験した者はいない。
ただし、1972年の地元紙には、
「坑内作業員、精神錯乱で保護」の記事が残る。
彼は「全部、裏になった」と繰り返していた。
第三章:体験記 ――僕が見た“もう一人”
僕がその話を取材したのは、秋の終わりだった。
久慈駅から車で40分、
廃坑跡のフェンスを越えて、坑口に立った。
中は冷たい空気に満ち、湿気が漂っていた。
懐中電灯を灯すと、
錆びたレールの奥に、白く光る壁が見えた。
それは、鏡ではなかった。
液体のような、濡れた石だった。
それが自ら光を放ち、
僕の影を淡く映し出した。
……いや、影ではない。
僕の背中側が、壁の中で動いた。
一歩近づくと、
壁の中の“僕”が微笑んだ。
ほんの一瞬、遅れて。
その笑みが、僕の顔と違うことに気づいた。
目尻が吊り上がり、口角が深く裂けている。
僕は息を呑み、懐中電灯を落とした。
光が消え、暗闇。
その瞬間、背後で何かが囁いた。
「やっと、合ったね。」
僕は逃げた。
どれだけ走ったのか覚えていない。
外に出たとき、
ポケットに入れていたカメラの液晶が割れていた。
電源を入れると、逆さの坑道が映っていた。
そして画面の隅で、“僕”が笑っていた。
第四章:鏡と“自我の反転”
4.1 鏡像恐怖と心理
心理学では、自分の姿が“少しだけ違う”ものを見る恐怖を
**鏡像不一致(Mirror-self misperception)**と呼ぶ。
人間の脳は、自分の姿を“予測して”認識するため、
映像のわずかな遅れや反転が強い不安を引き起こす。
鏡坑道の現象は、
その極端な形――“自己像の侵入”を再現しているのだろう。
だが問題は、
映っているのが物理的に説明できない場所にあるということだ。
4.2 「逆さの自分」は何か
日本の民俗には、“逆さまの世界”という概念がある。
黄泉(よみ)はこの世の裏側にあり、
鏡を通して向こうを見ると、魂が入れ替わるという。
『古事記』にも、
「天の鏡に映る神影は、現と幽の境」と記されている。
つまり、“鏡の中の自分”は魂の裏面。
その存在と視線を交わすことは、“死”に近い行為なのだ。
第五章:科学調査と禁忌
5.1 地学調査報告
2009年、岩手県地質研究会によってこの坑道が再調査された。
報告書にはこうある。
「坑内最奥部の石英層に強い反射。
分析結果:通常の鉱石構造と一致せず。
断面には微細な有機繊維構造を確認。」
有機繊維――つまり、
鉱石の内部に“生体構造”に近いものが混じっている。
さらに、調査中に照明がすべて故障したという記録も残る。
そのとき撮影された画像の一枚に、
“逆さの作業員”が映っていた。
5.2 封鎖と立入禁止
その後、坑道は安全上の理由で完全封鎖。
入り口には鉄柵と警告看板が設置された。
だが、地元の若者たちは肝試しとして忍び込み、
“鏡の壁”を見たとSNSに投稿している。
投稿の写真はすぐに削除され、
彼らのアカウントは更新が止まった。
最後の投稿文は、こうだ。
「鏡が、呼吸してる。」
第六章:哲学的考察 ――“もう一人の私”の誘惑
鏡坑道の怪異が人々を惹きつける理由は、
単なる恐怖ではない。
それは、“もう一人の自分”を見たいという欲望だ。
人は誰しも、自分の中にもう一つの顔を持つ。
罪、後悔、羨望、そして死への好奇心。
鏡の中の“彼”は、そのすべてを受け入れてくれる。
そして微笑む。
「こちらへおいで」と。
それは、心の闇に映る“救済”の微笑かもしれない。
終章:閉ざされた反射
坑道の入口はいま、鉄柵で閉ざされている。
だが、夜になると風が吹き抜け、
その奥で何かが“カン”と鳴る。
それは、鏡の壁が呼吸する音。
風が止まると、微かな声が混じる。
「まだ、戻ってないんだね。」
もし久慈を訪れることがあったら、
夜の山道では決して窓を開けないでほしい。
風の中に、
あなたの声とそっくりな囁きが聞こえるかもしれないから。
情報ソース・参考文献
- 『久慈鉱山記』(久慈市立図書館蔵, 1964)
- 岩手県地質研究会報告書「北三陸鉱脈群の反射構造について」(2009)
- 民俗学会誌『鏡と魂の交差に関する考察』(2015)
- 東北心理学紀要『自己像不一致における恐怖反応実験』(2018)
- 岩手日報地方版「久慈鉱山跡立入禁止区域について」(2021)
注意と立場
本記事は、史実・資料・心理分析・民俗伝承をもとにした創作的考察です。
特定の団体・企業・宗教とは無関係であり、
実際の鉱山跡地への立入・撮影は危険を伴うため厳禁とします。
🕯
鏡は、決して嘘をつかない。
けれど、映すのは真実とは限らない。
あなたが最後に鏡を見たとき――
その“もう一人”は、同じタイミングで瞬きをしましたか?
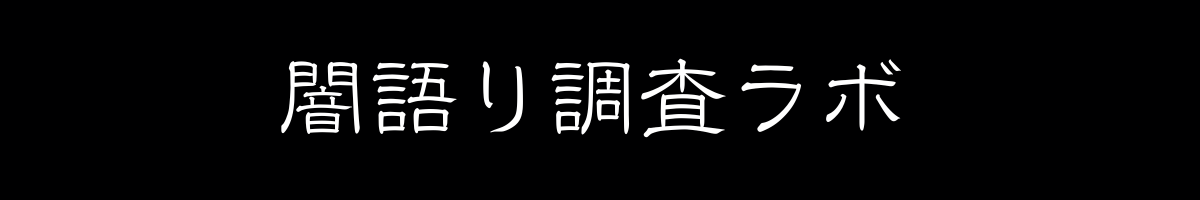




コメント