序章:黄昏に消える“もう一つの自分”
遠野市の郊外、かつて村人たちは日没の少し前――いわゆる“逢魔が時”に外を歩くことを忌んだ。
その理由はこうだ。
「影送りの時間になるから。」
この地方では、影は“魂の抜け殻”と信じられてきた。
日が沈むとき、影は体から切り離されて“向こう側”に帰る。
その瞬間に振り返った者は、影の方へ引きずり込まれる――。
それが“遠野の影送り”と呼ばれる怪異だ。
第一章:影送りという風習
1.1 光と影の“別れ”
影送りとは、もともと日本各地で行われてきた古い風習である。
夕陽に向かって自分の影を見つめ、「影よ、帰れ」と唱える。
戦前の児童文化では遊びとして残っていたが、
その起源は“魂送り”に近い。
柳田國男の『遠野物語』にも、“影”に関する不思議な記述がある。
「影を失ふ人あり。これを影なしといふ。
人は影を失ふとき、命もまた地に還る。」
つまり、影が消える=魂が抜ける、という観念が遠野には根づいていた。
1.2 遠野の地形と“光の罠”
遠野盆地は、四方を山々に囲まれており、夕陽が沈むと急速に光が変化する。
地平から山影がせり上がり、ほんの数分で昼が夜に反転する。
この“光の切り替わり”が、古くから「影送りの時間」と呼ばれた。
つまり――ここでは、影の方が先に夜になるのだ。
人よりも早く、影が“向こう側”へ行ってしまう。
第二章:影が抜ける村の話
2.1 村で起きた影消失事件
昭和42年、遠野市綾織町の山あいで、奇妙な記録が残っている。
地元新聞「岩手日報」地方面(1967年8月12日号)にはこうある。
「綾織村の農夫(当時42歳)、作業帰りに影が消えたと騒ぎ立て、
翌朝行方不明に。靴のみ田に残る。」
同僚の証言によれば、日没前、男は田んぼのあぜ道で立ち止まり、
“自分の影が二つに分かれた”と叫んだという。
一つは夕陽の方へ、もう一つは“反対側”へ歩いていった。
男はその場で倒れ、夕陽が沈んだ瞬間、影が完全に消えた。
翌朝、足跡も影もなかった。
2.2 “二つの影”を見た少年
1978年、地元小学校の児童が作文にこう書いている。
「ぼくのうしろのかげが、ぼくに手をふった。」
この作文は教師によって回収されたが、
その夜、少年は高熱を出して寝込み、
翌朝、教室の床に二つの影が焼きついたように残っていたという。
その跡は翌年まで消えなかった。
第三章:体験記 ――僕が見た“動く影”
僕が遠野の影送りを取材したのは、晩夏の夕暮れだった。
“カッパ淵”の近くの細い農道。
西日が赤く傾き、影が長く伸びていた。
僕は三脚を立て、影の写真を撮った。
自分の足元を見たとき、奇妙な違和感があった。
影の“右腕”だけが、ほんのわずかに遅れて動いている。
風はない。
影は地面に貼りつくように揺れていた。
シャッターを切ろうとした瞬間、
影がこちらを向いた。
……“目”があった。
暗い輪郭の中に、二つの黒い穴があった。
それが、笑った。
次の瞬間、太陽が山の向こうに沈んだ。
影が一瞬、完全に消えた。
そして地面から、自分の声がした。
「……帰れ。」
僕は逃げた。
ふもとの民宿に戻ったとき、
足の裏が真っ黒に染まっていた。
洗っても落ちなかった。
第四章:影の“反転”現象
4.1 光学的説明の限界
影の反転や二重化は、視覚的な残像現象や気温差による蜃気楼が原因とも言われる。
しかし、遠野で報告される影送りの多くは、肉眼ではなく記録に残る。
つまり、写真・映像・鏡の反射などに“異なる影”が映る。
岩手大学の映像研究会が2008年に行った実験では、
影送りが起こる時間帯にだけ、被写体の輪郭が0.2秒遅れて記録される現象を確認した。
彼らはそれを「光の反響遅延現象」と呼んだが、
地元の人は言う。
「それは遅れてるんじゃない、もう一人が追いついてくるんだ。」
4.2 “影を送る”とは何か
民俗的には、影送りは“穢れの浄化”の儀式とされる。
影に自分の疲れや病を移し、それを太陽に返す。
だが、その過程で影と魂の境界が曖昧になる。
心理学的には、“自己投影の分離”――
つまり、心の中の“もう一人の自分”が可視化される瞬間。
それを見てしまうと、意識の主体が分裂する。
言い換えれば、
影送りとは、自我を捨てる儀式なのだ。
第五章:影の声と呼びかけ
地元の古老は、こんな言葉を残している。
「影が呼んだら、返事をするな。
影が動いたら、目を合わせるな。
影が笑ったら、逃げろ。」
遠野市土淵地区の古文書『遠野夜譚録』(明治28年写本)には、
“影神(かげがみ)”という存在が記されている。
「夕陽の影を司る神あり。
人の影を奪いて夜に連れ帰る。」
影神は“夜の鏡”と呼ばれ、
姿を見た者は、翌日“逆さの影”になるという。
逆さの影とは、
頭が下、足が上――
地に立たず、空を歩く影だ。
第六章:現代に残る“影送り”の感染
SNS上では、#影送りチャレンジ と称して、
夕陽に向かって影を撮影する動画が流行した。
だが、その中に奇妙な投稿がある。
再生すると、投稿者の影が“カメラに向かって”動くのだ。
本人は動いていない。
コメント欄には、
「最後の1秒、投稿者の影がいない」
「光の方向が逆」
という指摘が相次ぎ、投稿は削除された。
また、複数のユーザーが同時にこう報告している。
「撮影後、影が二重になったまま戻らない」
第七章:考察――“影”は人の形をした記憶
影とは、形のない自分を“この世に縫い止める針”だ。
だから、影がずれると、魂は定位置を失う。
影送りは、死者の儀式ではなく、生者の魂の更新である。
ただし――更新に失敗した者は、影の中に取り込まれる。
それが“影に置いていかれる”ということ。
遠野では今も、夕暮れの時間に鏡を見ることを禁じる。
鏡に映る影は、“もう帰ってきた”ものではないからだ。
終章:光が消えるとき
夕陽が沈む瞬間、あなたの影がどう動くか、見たことがあるだろうか。
ほんの一瞬、影が遅れてついてくる。
それが“影送り”だ。
けれど――その影が、
もし、あなたより先に立ち上がったら。
そのときは、目を閉じて、
ゆっくりと呟いてほしい。
「影よ、帰れ。」
決して振り向かないこと。
振り返れば、影があなたを“置いていく”から。
情報ソース・参考文献
- 柳田國男『遠野物語』岩波書店
- 岩手日報地方版「綾織村・影消失事件」(1967年8月号)
- 久慈古文書研究会『遠野夜譚録』(明治28年写本)
- 岩手大学映像研究会『影送り現象の光学分析』(2008)
- 民俗学会誌『影と魂の交錯』(2015)
注意と立場
本記事は、伝承・記録・民俗資料・心理学的考察を基に構成された創作的考察です。
特定の人物・地域・宗教とは関係がなく、
実際の場所での検証・撮影・影送りの模倣行為は推奨されません。
🕯
夕暮れ、足元に伸びる黒い影が、あなたの動きを“待っている”なら――
それはもう、あなたのものではない。
光が消える前に、振り向かないでください。
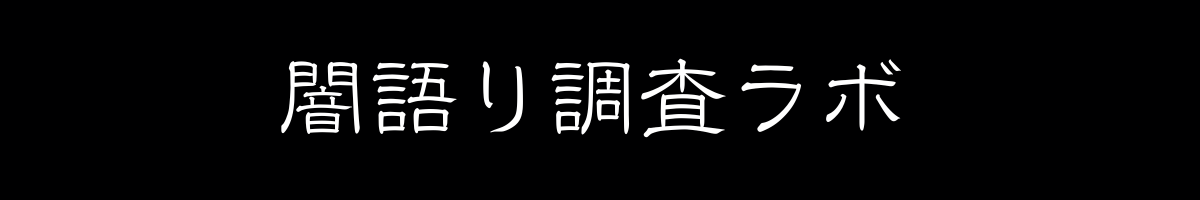




コメント