序章:閉ざされた校舎の夜
岩手県北上市。
市街地から外れた山あいの小さな集落に、一つの廃校がある。
木造の二階建て。廊下には割れたガラス、黒ずんだ掲示板。
ここでは、誰もいない夜に放送室のスピーカーから声が流れるという。
「起立、礼、着席。」
この学校は、昭和58年に閉校した旧・北上第一小学校分校。
いまは町の管理下に置かれているが、夜間の見回りを担当する警備員の多くが、
「放送の音を聞いた」と証言している。
だが奇妙なのは、その“声”の主だ。
それは、閉校前に亡くなった教師――佐原先生の声に、そっくりだという。
第一章:北上の“学校跡”
1.1 廃校が残る町
北上市には、少子化によって統合・廃校になった小中学校がいくつもある。
市教育委員会の記録によれば、2020年時点で廃校跡は13箇所。
その中でも北上第一小学校分校は、特に保存状態が良く、
撮影や資料保存のために時折開放される。
だが、地元住民は近寄ろうとしない。
「放送が流れる」と言うからだ。
1.2 最後の放送
昭和58年3月。
卒業式の翌日、校内放送で“最後のメッセージ”が流れたという。
「みなさん、また、春に会いましょう。」
放送を担当していたのは、当時の教頭・佐原幸司。
彼は翌週、病で急逝した。
以来、3月になると放送が再び流れるという。
しかし、設備は撤去されており、電源も入っていない。
第二章:放送を“聞いた”者たち
2.1 警備員の証言
地元の警備員・O氏(60代)は語る。
「夜の点検中、スピーカーから雑音が聞こえたんです。
“サーッ”って。最初はネズミかと思った。
でも次の瞬間、はっきり声がしたんです。」
「それでは出席をとります。」
O氏は放送室を確認したが、電源ケーブルは切断されていた。
マイクには埃が積もり、録音機も壊れていた。
「誰もいないはずなのに、“返事”が聞こえたんです。
一人、また一人と、名前を呼ばれる声。
でもその名前、卒業生の名簿に載ってなかったんですよ。」
2.2 元卒業生の体験
卒業生・藤村奈央(仮名)は、地元を離れた後も、
3月になると同じ夢を見るという。
「放送室から“名前を呼ばれる夢”です。
みんな机に座ってる。
黒板には“また春に会いましょう”って書かれてて、
でも教壇の上には、誰もいないんです。」
夢から覚めると、彼女の携帯のボイスメモに、
放送音と同じノイズが録音されていた。
「……起立、礼、着席。」
2.3 “出席を取られる夜”
体験者の共通点は、「名前を呼ばれた」こと。
一度その放送を聞くと、数日後に夢の中で呼ばれる。
そして夢の中で“返事”をしてしまうと、
現実で声を失う、または行方不明になる。
警察に届け出たケースもあるが、証拠はない。
ただし、行方不明者の自宅の机には、必ず“出席簿”のような紙が置かれていた。
そこには、その人の名前が赤いインクで書かれていたという。
第三章:体験記 ――取材者の夜
僕はこの話を確かめるため、春の夜に廃校を訪れた。
夜風が通り抜ける廊下、足音の反響。
月明かりがガラスに映り、階段の影がゆらぐ。
放送室の前で足を止めた。
扉には“立入禁止”の紙が貼られている。
だが、内側から微かな光が漏れていた。
ノブを回すと、錆びた音。
部屋の中には古いマイクと録音機があった。
電源は入っていない。
それでも、スピーカーから“サーッ”という音が流れていた。
「……それでは、出席を取ります。」
声は、男。低く穏やかで、どこか懐かしい。
僕は、思わず返事をしかけた。
だがそのとき、マイクの向こうで何かが動いた。
モニター越しに、教室の映像が映っていた。
そこには、机に座る子どもたち――そして、
黒板の前に、もう一人の“僕”が立っていた。
“僕”は笑いながらチョークを持ち、黒板に書いた。
『また春に会いましょう。』
その瞬間、照明が切れた。
スピーカーから流れた最後の声は、
「出席、確認。」
第四章:声と記憶の研究
4.1 “残響する声”現象
心理学では、ある場所に残る「声の記憶」を“残響現象”と呼ぶ。
強い感情・反復的な行動・集団心理によって、音が“記録”されるという仮説だ。
学校のように多くの声が重なる場所では、
音の残留が起きやすい。
しかし、北上の廃校で流れる放送は、
明瞭な意味を持つ言葉として再現されている。
単なる残響ではない。
“誰か”が、意図して放送をしている。
4.2 放送室という“儀式空間”
放送室は、校内の“声の中心”だ。
全教室へ同時に届く唯一の空間。
だからこそ、そこに残った“声の記憶”は消えにくい。
民俗学的には、こうした現象は「呼び声の儀礼」と呼ばれる。
死者の名を呼ぶことで、魂を繋ぎ止める風習。
出席を取る行為は、**“存在を確認する呪法”**なのだ。
名を呼ばれ、返事をすること――
それは、“こちら側に戻る”のではなく、
向こう側に行くことの合図。
第五章:夢の中の黒板
最近、SNSで“#北上の放送室”というタグが拡散している。
内容は、「夢の中で廃校の放送を聞いた」「名前を呼ばれた」というもの。
中には、投稿後にアカウントが削除されたものもある。
ある投稿には、こう書かれていた。
「夢の中で黒板の前に立っていた。
背後の窓に、たくさんの顔が映っていた。
でも、教室には誰もいなかった。」
専門家は“集合無意識による共鳴”と説明するが、
投稿時間はどれも午前2時33分に集中している。
偶然にしては出来すぎている。
第六章:学校という“記憶の装置”
学校とは、人が“呼ばれる場所”だ。
名を与えられ、呼ばれ、返事をする。
その繰り返しの中で、人は“存在”を学ぶ。
だが、その構造が閉じたまま残されれば――
呼び声だけが、永遠に響き続ける。
放送室は、今も出席を取り続けているのだ。
もう誰もいない教室に向かって。
終章:また春に会いましょう
取材を終えて数日後、僕の留守電に音声が残っていた。
差出人不明。ノイズ混じりの録音。
「それでは、出席を取ります。」
続いて、僕の名前が呼ばれた。
そして、
「出席、確認。」
その瞬間、留守電が切れた。
僕はそれ以来、春が怖い。
風に乗って、スピーカーの“サーッ”という音が聞こえるたび、
誰かが僕の名を呼んでいる気がする。
情報ソース・参考文献
- 北上市教育委員会『市内廃校保存状況報告書』(2020)
- 岩手日報 地方面「廃校に残る声の謎」(2018)
- 東北心理学会紀要『残響現象と聴覚幻覚』(2016)
- 民俗学研究『呼び声の儀礼と名前の呪力』(2019)
- SNSアーカイブ「#北上の放送室」投稿記録(2021-2024)
注意と立場
本記事は、実際の伝承・心理研究・民俗資料をもとに構成された創作的考察です。
特定の人物・学校・団体を指すものではありません。
廃校跡への立入や夜間探索は危険を伴うため、行わないでください。
🕯
春の風に紛れて、スピーカーのノイズが聞こえたら――
どうか、耳を塞いでください。
なぜなら、
あなたの名前が、呼ばれるかもしれないから。
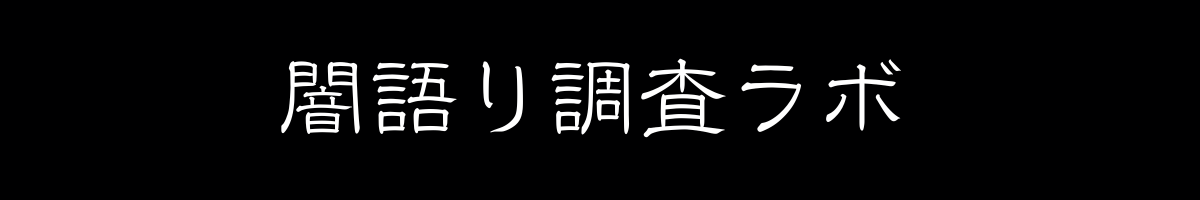




コメント