権力は、声を荒げて人を支配するのではない。
静かに――沈黙によって支配するのだ。
🔹 事件の朝

1995年3月30日、午前8時30分。
東京都文京区音羽。
出勤途中の國松孝次警察庁長官(当時)が、自宅マンション前で銃撃された。
犯人は、至近距離から自動拳銃を4発発射。
胸、腕、太腿に3発が命中したが、奇跡的に命をとりとめた。
事件発生から数分後、報道各社の速報が走る。
「警察庁長官、銃撃され重傷。」
日本中が凍りついた。
捜査史上最大規模の捜査が展開された。
延べ20万人の警察官が動員され、
周辺の監視カメラ、弾道、証拠物件が洗い出された。
だが、犯人の影は一度も捕捉されなかった。
それでも、この事件の「真相」は、最初から定められていたのかもしれない。
🔹 組織の内側で起きていた“歪み”
1990年代、日本社会はオウム真理教事件によって揺れていた。
地下鉄サリン事件、坂本弁護士一家殺害、松本サリン事件──
宗教と暴力が国家の秩序を侵食し始めていた。
一方、警察内部でも変化が起きていた。
オウム捜査を主導する公安部と、従来の刑事捜査を重んじる刑事部。
その溝は、組織の根を断ち割るほど深かった。
公安は「国家の防波堤」であり、
政治との結びつきが強い。
一方の刑事部は、現場と市民の距離が近く、
“泥臭い捜査”の誇りを守ろうとしていた。
1995年春、その対立が頂点に達する。
警察庁の上層部では、公安主導の再編計画が進められていた。
その矢面に立っていたのが、國松孝次長官だった。
彼は組織改革を掲げ、
“政治に依存しない警察”を理想としていたという。
──だが、理想を掲げる者は、いつも最初に撃たれる。
🔹 「公安の粛清説」とは
この事件における“公安の粛清説”とは、
単なる陰謀論ではない。
**警察内部の勢力争いを整理するための“静かな粛清”**が行われたのではないか、
という仮説である。
狙撃事件の後、公安部は前例のない権限拡大を遂げる。
対テロ・防諜部門の統合、情報機関との連携強化。
そして、刑事部の権限は相対的に縮小していった。
この変化のスピードが“偶然”であると信じるのは難しい。
🔹 “異常な初動”が意味するもの
事件直後、異例の決定が下された。
通常なら刑事部が担当する銃撃事件を、公安部が主導するという。
その理由は「宗教団体の関与が疑われるため」。
だが、現場にオウム信者を示す証拠は一つもなかった。
(出典:文藝春秋オンライン)
にもかかわらず、捜査は最初から“オウム報復説”を前提に進められた。
他の可能性――怨恨、政治的対立、内部犯行――は、
「捜査対象外」として切り捨てられた。
この時点で、事件の行方は決まっていたのだ。
さらに、元警察官による自白や、匿名の内部告発文書も現れた。
だが、どれも「信用できない」「精神的に不安定」として排除された。
捜査本部の資料には、彼らの名も証言も残っていない。
まるで、“真実の芽”が組織的に摘まれたかのようだった。
🔹 秩序を守るための“犠牲”
事件後、公安部はかつてない影響力を手に入れる。
内閣情報調査室、警備公安部門、防衛庁情報部との連携が強化され、
国家的な情報監視体制が整った。
対テロ法案、オウム対策法案の成立も、狙撃事件後に加速した。
この変化を偶然と呼ぶには、あまりに出来すぎている。
──國松長官の撃たれた3月30日を境に、
日本の治安システムは**“公安国家”型**へと舵を切ったのだ。
粛清説は、こうした一連の変化を「副産物ではなく目的だった」とみる。
つまり、事件は権力構造の再構築――
秩序を守るための“儀式”だったのではないかということだ。
🔹 沈黙する国家
事件から15年、2010年に時効を迎えた。
だが、未だに多くの資料が非公開のままである。
(出典:朝日新聞デジタル)
「関係者の捜査には政治的制約がある」
──内部文書に残るこの一文が、すべてを語っている。
本来、真実は法の下で明らかにされるべきだ。
だが、ここでは法こそが沈黙を支える“壁”になっている。
国家は、真実を隠すために嘘をつく必要はない。
ただ、“語らない”ことを選べばいい。
🔹 終章:沈黙の秩序
犯人がわからない事件より、
「犯人を語れない事件」の方が恐ろしい。
國松長官狙撃事件は、未解決というよりも、未解明のまま放置された事件だ。
そこには“意図的な沈黙”がある。
沈黙とは、秩序のための装置。
権力は、声を発さずして人を支配できる。
もしこの事件が、国家の内部秩序を守るための粛清だったとしたら――
真犯人は、人ではなく“体制そのもの”だったのかもしれない。
真実は、語られない時に最も強く存在する。
そして、沈黙は秩序のための言葉である。
📖 次の記事へ ▶
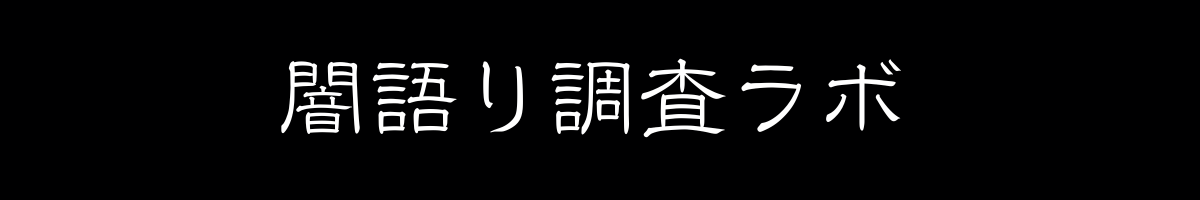
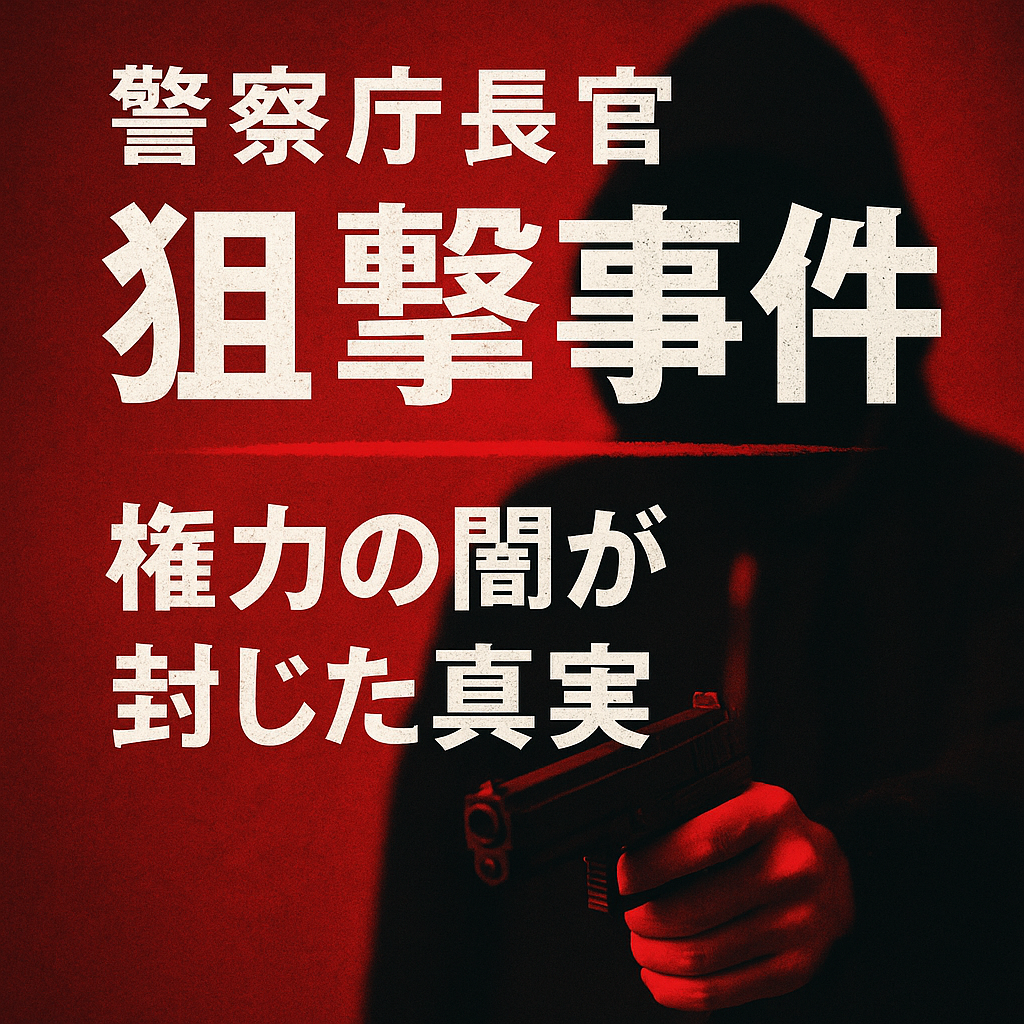
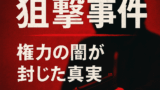

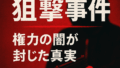
コメント