真実を語ろうとした者は、誰もいない。
いや――語らせてもらえなかったのかもしれない。

🔹 消された告発
國松長官狙撃事件の直後、
警察庁記者クラブに一通のワープロ文書が届いた。
差出人不明。
だが内容は、ぞっとするほど内部事情に精通していた。
「國松長官を撃ったのは、警察内部の人間だ。
捜査は、上層部の意向で歪められている。」
文書の一部は、報道されていない現場情報と一致していた。
それでも警察は「悪質ないたずら」として処理した。
この告発文の存在は、
当時の記者の証言によって事実として残っている。
(出典:voice.php.co.jp)
だが、文書はほどなくして回収され、
警察庁の記録からも姿を消した。
まるで、「最初の声」を社会から削除するかのように。
🔹 “自白”した元警察官
翌1996年、ある元巡査長が突然、「自分が撃った」と自白した。
彼は精神的に不安定で、供述には矛盾が多かったとされる。
捜査当局は「信用性なし」と判断し、立件を見送った。
しかし、彼の供述には誰も知らない現場の細部が含まれていた。
現場付近の監視カメラの死角、銃の種類、弾道の角度――。
それらは報道にも出ていない情報だった。
この「偶然の一致」を、当局は一切説明しなかった。
やがて男はメディアからも姿を消し、
その自白は“無かったこと”にされた。
報道記事も削除され、名前も伏せられた。
「声を上げた瞬間、世界が音を失う。」
まさにそれを体現するような出来事だった。
🔹 沈黙する組織
警察という組織は、上下関係が絶対だ。
現場の声よりも、秩序と統制が優先される。
上の命令が「無かったことにしろ」なら、
部下は何も見なかったことにする。
この事件では、まさにその構図が露骨に現れた。
複数の関係者が取材に対してこう証言している。
「あの頃、何かを言えば“オウム対策を妨害した”と責められた。
誰も反論できる空気じゃなかった。」
(出典:mainichi.jp)
沈黙は、命令ではない。
空気として植えつけられる。
それは、声を封じる最も穏やかで確実な方法だ。
🔹 “内部告発者説”が意味するもの
この仮説が示唆するのは、
事件の裏に「語られなかった真実」が存在したということ。
──誰かがそれを告げようとした。
だが、その声は潰された。
日本の警察組織には、
「内部告発」という文化がほとんど存在しない。
内部で異論を唱えることは、自己否定と同義だからだ。
もし本当に“内部の人間”が関与していたとしても、
それを証明するには、上司を告発しなければならない。
それはすなわち、自らの職を失うことを意味する。
だから、誰も語らない。
語れない。
🔹 記録の“再構成”
事件の報告書には、多くの“空白”がある。
証言が途中で切られていたり、日時が前後していたり。
当時の捜査員の一人は、こう語っている。
「あの報告書は、後から作られた部分がある。
まるで物語のように、整いすぎていた。」
(出典:books.bunshun.jp)
記録は“事実”ではなく“公式見解”になる。
事実を消すより、別の事実で上書きするほうが簡単だ。
告発者の声が消えても、
報告書は静かに“真実”を語り直す。
それが、国家という巨大な編集装置の仕組みだ。
🔹 組織心理 ― なぜ封じるのか
内部告発が起これば、
組織は「正義」と「体面」の間で揺れる。
正義を取れば、体制が崩れる。
体面を取れば、正義が死ぬ。
警察という巨大な共同体では、
“正義よりも沈黙が安全”という心理が根深く存在する。
上司を守ることが忠誠であり、
沈黙を保つことが“秩序”だと教え込まれている。
そして、その秩序が真実よりも重く扱われる。
この事件が未解決のままである理由の一端は、
まさにその心理構造の中にある。
🔹 終章:声なき証人
真実は語られなくても、確かに存在する。
それを証明するのが、“沈黙”という名の証拠だ。
國松長官狙撃事件の「内部告発者説」は、
単なる噂ではない。
それは、正義を封じる社会の鏡だ。
真実を知る者たちは、いまも沈黙の中にいる。
だが、沈黙の裏側には、確かに“誰かの声”が響いている。
事件は時効を迎えても、
その声は消えない。
なぜなら、沈黙とは――
語れない者たちの、最後の言葉だから。
📖 次の記事へ ▶
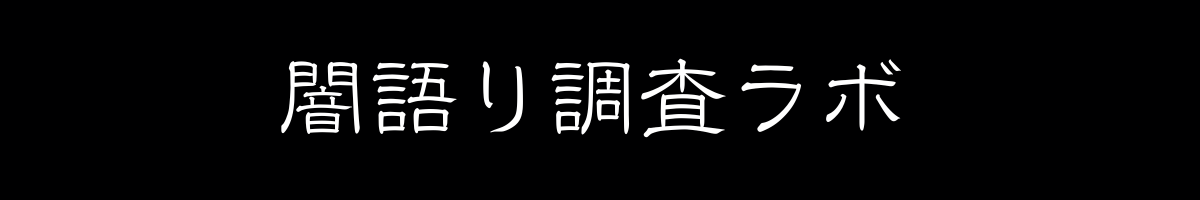
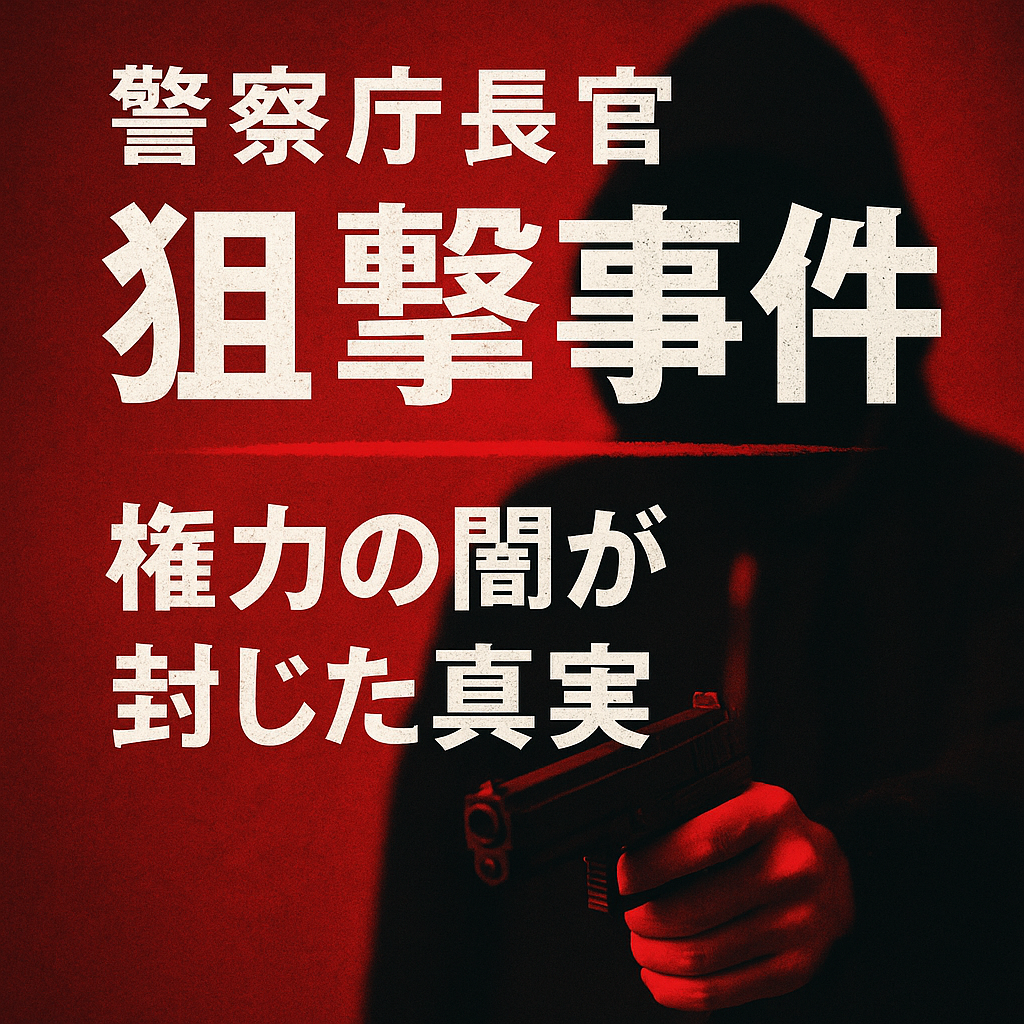
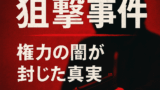

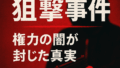
コメント