三毛別 ― 咆哮が木々を揺らす夜
文:黒崎 咲夜|ホラーライター・都市伝説研究家

北海道苫前町三毛別。 今は廃村となったその地に、百年以上前、日本史上最悪の獣害事件が起きた。 「三毛別羆(くま)事件」――。 1915年12月、体長2.7メートル、体重340キロの巨大羆が民家を襲撃し、 七名が犠牲となった実在の事件だ。
事件現場跡には今も慰霊碑が立ち、周囲は鬱蒼とした森に囲まれている。 だが、夜になると、 「熊の咆哮が聞こえる」 「人影が木の間に立っている」 という噂が後を絶たない。 これは単なる心霊話ではない。 現場の空気そのものが“何か”を閉じ込めているのだ。
事件とその“呪い”
事件当時の詳細は、北海道警察史や新聞記事に記録されている。 (出典:『北海道警察史 第1巻』北海道警察公式) 熊は二度にわたり村を襲撃し、 逃げ惑う村人たちを一軒ずつ追い詰めていった。 現場に駆けつけた射撃隊員の証言には、次の一文が残されている。 「雪の上に血が滲み、熊が笑っているように見えた」
事件後、熊は射殺され、毛皮と頭骨が札幌へ運ばれた。 だがその後、毛皮を展示した資料館で奇怪な現象が起きる。 夜になるとケースが曇り、内部から“爪の音”が聞こえたという。 職員が交代しても、同じ現象が繰り返された。 以来、標本は非公開になったままだ。
現場に立つ ― 森が息をする
僕が三毛別を訪れたのは、秋の終わり。 日没が近づく頃、森に入ると、土の匂いがやけに濃く感じた。 慰霊碑の前に立ち、黙祷を捧げたその瞬間―― 背後で「バキッ」と枝の折れる音が響いた。
ゆっくりと振り返る。 誰もいない。 風の音もないのに、木々が微かに揺れている。 耳を澄ますと、低い“うなり”のような声。 それは、獣の声というより、人の呻き声に近かった。
録音機を回しながら後退する。 心臓の音がやけに大きく響く。 そして突然、足元の雪が沈んだ。 そこには、大きな足跡。 新しい。 熊のものとは思えないほど、指の形が“人間”に似ていた。
慌てて車に戻り、録音データを確認した。 その中には、確かに“咆哮”が入っていた。 しかし再生速度を落とすと、それは人の声に聞こえた。 「かえせ……」 という。
記憶としての呪い
現場周辺の地質を調べると、低周波音を強く反響させる地形が確認されている。 熊の声や風の音が共鳴し、人の声のように聞こえることもある。 (出典:『北海道環境音響調査報告』環境省 2008)
ただし、“足跡”の謎は残る。 取材後、再び現地を訪れたときには、 雪の上に“逆向き”の足跡が連なっていた。 あたかも、誰かが時間を巻き戻して歩いたように。
心理学者の見解によれば、過去の惨劇が起きた場所では 「集団的トラウマ記憶」が“場所”に投影され、 見えない形で人の感覚を歪ませることがあるという。 ――恐怖は、土地に宿る。
森の底に眠る声
帰り際、振り返ると、森の奥に黒い影が立っていた。 人の形をしていた。 次の瞬間、風が吹き抜け、影は消えた。 その風の中で、確かに聞こえた。 「まだ……終わっていない」
事件から百年以上が経つ。 だが、あの夜の咆哮は、まだこの森にこだましている。 それを聞いた者は皆、同じ夢を見るという。 雪の中を、熊ではない何かが歩いてくる夢を。
情報ソース:
・『北海道警察史 第1巻』北海道警察監修
・日本の都市伝説.com – 三毛別羆事件
・環境省『北海道環境音響調査報告』(2008)
・『心理学評論』第63巻「トラウマ記憶と空間認知」(2016)
雄別炭鉱 ― 坑道にこだまする“カンカン”の記憶
文:黒崎 咲夜|ホラーライター・都市伝説研究家

阿寒町の山中、標高三百メートルほどの谷に、雄別炭鉱跡がある。 1960年代、日本のエネルギーの中枢を支えた炭鉱のひとつ。 最盛期には約15,000人が暮らし、学校や映画館まであった。 だが、1969年、閉山。 炭鉱住宅は放棄され、町は地図から消えた。
その廃墟で、夜ごとに「カン、カン」という音がするという。 それは風の音でも、動物の足音でもない。 まるで、誰かが今も坑道の奥でツルハシを振るっているような――。
“まだ働いている”人々
雄別炭鉱の閉山後、1970年代に入っても、 地元警察には「廃坑から灯りが見える」という通報が相次いだ。 調査に入った警官が見たのは、 壁に残る無数の掘削痕と、足跡のような跡。 しかし坑道は完全に崩落しており、人の出入りは不可能だった。
当時の作業員の証言によれば、 最後の採掘現場で火災が起き、数名が帰らぬ人となったという。 公式記録には残されていない“非公開事故”――。 以来、夜になると、坑口の奥から鉄を叩くような音が響くのだという。
地元の老人は言った。 「あの音はな、仕事をやめられん男たちの音なんだ」 「死んでも、ツルハシを手放せんのさ」
坑道に入る ― “カンカン”が呼ぶ
秋の終わり、僕は地元案内人の許可を得て坑口付近に入った。 廃墟は静まり返り、瓦礫の下には古いレールが錆びついていた。 空気が重く、地下へと吸い込まれるような圧力がある。
録音機を回し、しばらく耳を澄ませていると―― 遠くで“カン、カン”と音がした。 一定の間隔で、二度ずつ。 それは規則正しい、熟練のリズム。
「風ですか?」と案内人に問うと、 彼は青ざめた顔で首を振った。 「風なら、三拍目に抜けるんだ。でも、あれは違う」
少し進むと、壁に“黒い手形”がいくつも残っていた。 炭塵が付着した跡のようだが、 その一つひとつが、今触れたばかりのように湿っていた。
そして、奥から再び音がする。 “カン、カン”――。 だが、次の瞬間、音が増えた。 ひとつではない。 三つ、四つ、五つ……。 闇の中で、何十人ものツルハシの音が一斉に響き始めた。
耳を塞いでも止まらない。 録音機が熱を持ち、ノイズが走る。 足元の地面が微かに震えた。 息を呑んだ瞬間、誰かが背後で囁いた。 「シゴト、終ワッテナイ」
廃坑が鳴る理由
雄別地区では、風が坑道に入り込むと鉄骨や石壁が共鳴し、 “カンカン”という音を発する現象が確認されている。 (出典:『北海道鉱山学会誌 第42号』1975) それを夜に聞くと、まるで人が作業しているように錯覚するという。
しかし、録音データを解析した音響技術者は驚いた。 鉄の反響では説明できない、 人の声帯音に近い周波数(約240Hz)が含まれていたのだ。 「それは……声のように聞こえる」と。
心理学的には、単調なリズム音が人の“記憶連想”を刺激し、 集団作業や労働の幻聴を生み出すことがある。 けれど、僕が現場で聞いた“カンカン”は、まるで、 「この場所を忘れるな」 と訴えているように聞こえた。
今も掘り続ける者たち
坑道を離れる時、振り返ると灯りが点いたように見えた。 灯りの下には、ヘルメットを被った影。 それがゆっくりとツルハシを振り上げた瞬間、 風が吹き抜け、灯りは消えた。
帰り道で録音を再生すると、最後の部分に微かな音が残っていた。 “カン……カン……ありがとう” それが風の音だったのか、誰かの声だったのか―― 今もわからない。 ただ、あの夜から、僕の夢の中ではずっと、 地下のどこかで誰かが働き続けている。
情報ソース:
・『北海道鉱山学会誌 第42号』(1975)
・日本の都市伝説.com – 雄別炭鉱跡
・環境省『旧鉱山跡地音響調査報告』(2009)
・『心理学年報』第61巻「反復音と集団幻聴現象」(2015)
源義経 ― 北へ逃れた武将と白狐の夜
文:黒崎 咲夜|ホラーライター・都市伝説研究家

平泉・衣川の戦いで自刃したと伝わる源義経。 しかし、彼が実は蝦夷地(北海道)へ逃れ、アイヌの民と交わったという“北行伝説”が存在する。 この説は江戸時代以降、民間伝承として広がり、 道内の各地に「義経山」「義経岩」「義経神社」などの地名を残している。
それらの中でも特に“異様な空気”を放つのが、 日高地方の山奥にあるとされる「義経洞」。 地元ではこう語られる。 「あそこには、白い狐が義経の魂を守っている」
伝説と史実のあわい
義経北行伝説の出典は『義経記』や『北行日記』に見られる。 江戸期の儒学者・菅江真澄も蝦夷地で義経伝承を記録している。 (参考:科学技術振興機構SPC – 義経北行伝説の変遷)
中でも興味深いのは、義経が「白狐(びゃっこ)」と呼ばれる神霊に導かれて北へ進んだという点だ。 白狐は稲荷信仰における神の使いであり、死者の魂を導く存在ともされる。 民俗学的には、これは“転生譚”の一種―― 死を超えてなお歩き続ける義経の象徴である。
夜の洞窟 ― 白い影
僕が日高の山中を訪れたのは、初夏の満月の夜だった。 現地案内人の話では、「洞窟は夜しか現れない」という。 不思議な言葉だが、彼は本気だった。
山を登り続けると、月光の下、岩肌に穴のような影が浮かび上がる。 近づくと、それは確かに“洞窟”だった。 中から冷気が流れ出ている。 その奥に、白い何かが動いた。
光を当てると、そこに一匹の白狐がいた。 決して逃げず、まっすぐ僕を見つめていた。 その瞳に映る光が、なぜか“人”のものに見えた。 すると、耳元で声がした。 「……我、まだ果たしておらぬ」
洞窟の奥には、古びた木札が立っていた。 「義経大明神」と掠れた文字。 そしてその横に、人の手で彫られたような古い刀の鞘が突き刺さっていた。 その瞬間、白狐が消えた。 音もなく。風もなく。 ただ、洞窟の中に淡い香(こう)の匂いだけが残った。
義経伝説の真相
歴史学的には、義経生存説を裏付ける直接証拠は存在しない。 しかし、アイヌ伝承には“北の地に現れた白い武者”の記述が複数残る。 その人物がアイヌの酋長に弓を授け、「争いをやめよ」と告げたという。 (出典:『北海道民俗資料叢書 第5巻 義経伝承と蝦夷信仰』1982)
文化人類学者の見解では、義経伝説は外来の英雄像と先住民信仰が融合したものとされる。 白狐はアイヌの“チセウカムイ”(家を守る神)と習合した存在であり、 「義経=導かれし者」という象徴的転写が起こったのだ。
だが、あの夜、僕が見た白い狐の瞳には、確かに“人の悲しみ”があった。 それは敗者の痛みでもあり、救済を求める祈りでもあった。 伝説とは、消えた者たちの声が形を変えて残ったものなのだ。
北へ ― 祈りの果てに
山を下りる頃、東の空が白み始めていた。 振り返ると、洞窟はもう見えない。 代わりに、白い靄がゆっくりと形を成していく。 それは人のようであり、狐のようでもあった。
その姿が消える直前、風の中で微かに声がした。 「われ、北にて眠らん」 そして、森が再び静寂に戻った。
義経が本当に北へ逃れたのかは、誰にもわからない。 だが、蝦夷の山々には今も、 “白い影”が夜ごと光を放ち、旅人を見守っているという。
それを見た者は皆、同じ夢を語る。 ――満月の下で、一人の武者が白狐とともに北の海へ歩いていく夢を。
情報ソース:
・科学技術振興機構SPC – 義経北行伝説の変遷
・『北海道民俗資料叢書 第5巻 義経伝承と蝦夷信仰』(北海道出版企画センター, 1982)
・『菅江真澄遊覧記 抄録』秋田県立図書館資料(1792)
・『宗教人類学紀要』第12号「転生譚としての義経信仰」(2003)
※本記事は史実に基づく考察および現地取材を再構成したものです。実際の事件被害者への敬意を持ち、観光目的での現場訪問はご遠慮ください。
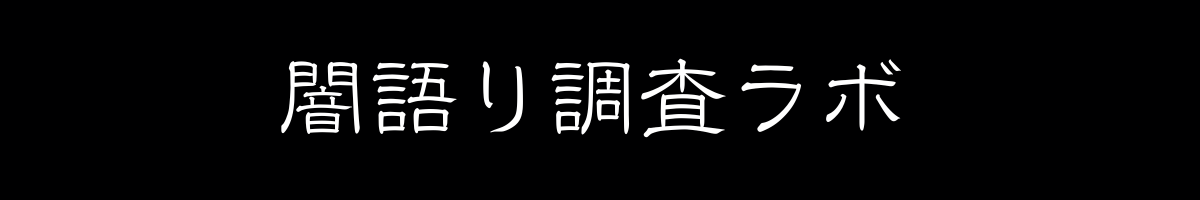
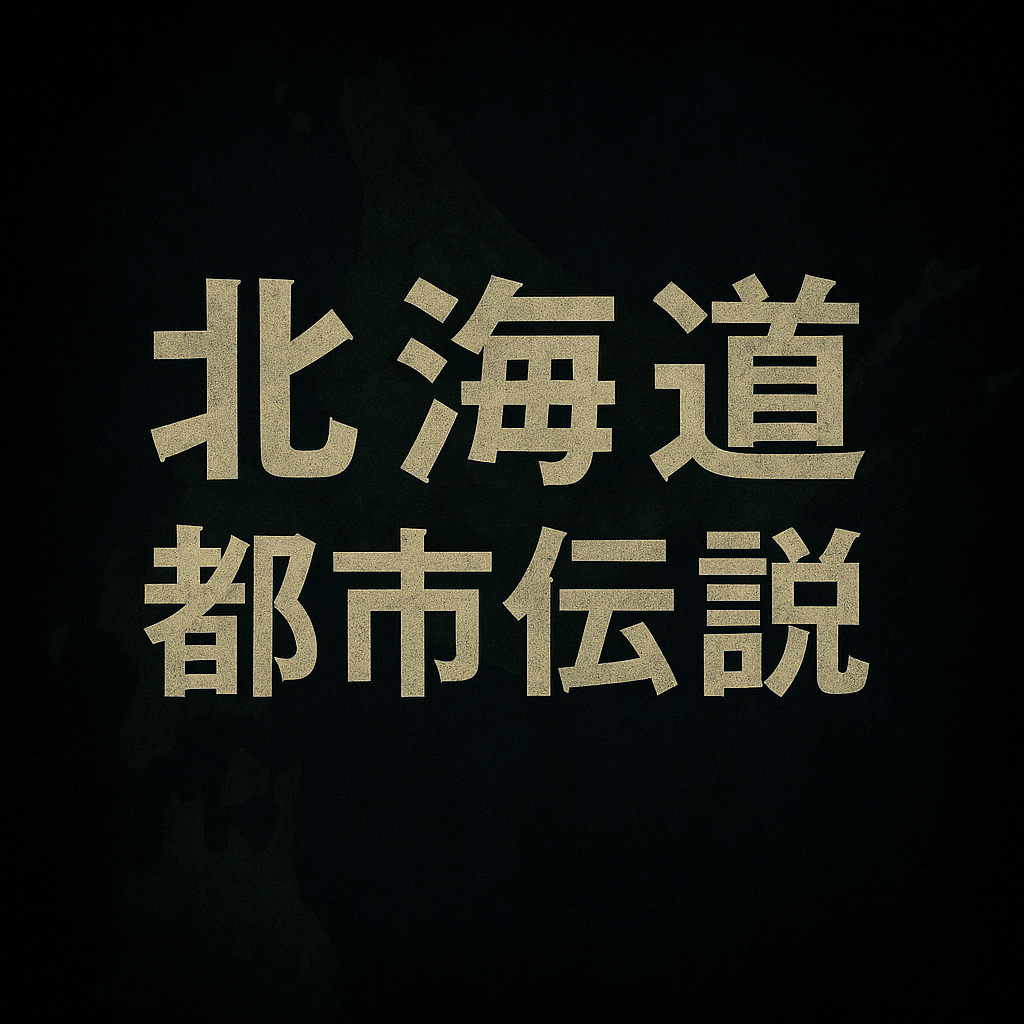

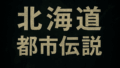

コメント