――壁の向こう、誰かの足音を聴く夜
第1部 闇の間取りに招かれて
夜。部屋の影が伸びて、壁紙の継ぎ目が濃くなったとき、私は思う。
「この家には、まだ帰ってこない誰かがいるのではないか」と。
映画の題名が「事故物件ゾク 恐い間取り」。
それだけで、心の奥に冷たい予感が立ち上る。
事故物件。つまり過去に“死”や“事件”を含んだ住居だ。
そこに住むとは、見えない過去と共存することでもある。
本作は、ノンフィクション怪談で知られる松原タニシ氏の著作『事故物件怪談 恐い間取り』シリーズを原作とし、
日本ホラー映画界の名匠 中田秀夫 が監督を務めた。 ウィキペディア+2松竹ムービー+2
「事故物件住みますタレント」という設定を主軸に、
恐怖と日常、メディア消費の狭間に潜む怪異を紡ぎ出そうとする意図が強く感じられる作品だ。
主演には、Snow Man の 渡辺翔太 が抜擢され、
ヒロインに 畑芽育、また吉田鋼太郎らが脇を固める。 映画.com
そのキャスティングも含めて、ホラーとしての期待感と興行性を同時に担おうとする意気込みが伝わってくる。
劇場公開は 2025年7月25日。上映時間は約 113 分。 東宝シネマズ+2映画.com+2
そして、この作品は公開前からひとつの“挑戦”を盛り込んでいた。
“恐さゾクゾク度”を 5 段階から選べる上映方式という試みだ。観客自身の耐性を反映させる、体験型ホラーの萌芽。 松竹ムービー
(“恐さマシマシ”絶叫上映、4DX での強化上映、音量控えめ版など多彩な選択肢) 松竹ムービー+2松竹ムービー+2
──この“観客と恐怖の距離を調整できる”仕掛けが、本作の設計意図を象徴しているように思える。
私が劇場で体験したのは通常上映。
だが、スクリーンの闇に踏み込むほどに、私は思った。
この物語は「見る恐怖」だけでなく、「選ぶ恐怖」でもあるのだと。
第2部 あらすじ ―― 事故物件を巡る迷宮
福岡から上京した 桑田ヤヒロ(渡辺翔太)は、芸能界で芽が出ずジリジリと焦る日々を送っていた。
あるきっかけで“事故物件住みますタレント”としての活動を始めることになる。 映画.com
すなわち、「いわくつきの家」に住み、そこで起きる怪奇現象を記録し、番組や SNS ネタとして発信する仕事だ。
ヤヒロは、いくつもの事故物件を転々とする。
「必ず憑りつかれる部屋」「いわくつきの古い旅館」「降霊するシェアハウス」など、舞台は多岐にわたる。 松竹ムービー+2映画.com+2
彼の体質は“憑かれやすい”とされ、感受性が強いゆえに、怪奇現象が彼を直撃する。
最初の物件では、女性が殺害された部屋に入る。
風呂場、鏡、床、壁――すべてが過去を映し出すような設計だ。
ヤヒロは映像を回しながら、徐々に異変を感じ始める。
物語が進むにつれ、主人公とヒロイン・春原花鈴(畑芽育)との関わりも深まる。
花鈴はヤヒロの活動をある程度理解しつつ、恐怖と不信の間で揺れる存在として描かれる。
中盤、ヤヒロはある“最恐事故物件”へと案内される。
そこでは、従来の怪奇現象を超える“想像を絶する恐怖”が待っており、真実の一端が暴かれていく。
亡霊・気配・鏡・家屋構造の歪み──これらが交錯し、ヤヒロは自らの心の深淵と向き合うことになる。
結末に向けて、ヤヒロは“ただの被写体”から“償いを背負う者”へ深化していく。
家と過去、観客とコンテンツの関係性が崩れ、最後には“間取りそのものの呪縛”と対峙する。
(以降、ネタバレを織り込みつつ核心に迫る語りへ移行する。)
第3部 恐怖の構成、演出、技巧の分析
『事故物件ゾク 恐い間取り』の恐怖は、ジャンプスケアの連打でも、過激な視覚ショックでもない。
むしろ、それらを抑えつつ“日常の歪み”を見せることで、観客の神経をじわじわと蝕んでいく。
1. 間取りと空間設計の恐怖
“間取り”という語には、建築の設計図、生活動線、住まいの倫理が込められている。
この作品では、その“間取りの歪み”が恐怖の主題になる。
壁が消えたり歪んだり、部屋と廊下の境界が曖昧になる場面が複数登場する。
例えば、風呂場と鏡との距離感が狂うシーン、
窓の外の風景と内観が重なり合う場面、
廊下を進むと先がないように見える鏡面の反射など、
空間そのものが罠になる演出が徹底されている。
このような“住居空間”の怖さは、『リング』『着信アリ』といった邦ホラーのクラシックを参照しつつ、
より“近しい恐怖”を目指しているように感じられる。
2. 音響・静寂の操作
音。音はこの映画の血潮だ。
水滴の音、足音、扉のきしみ、風のざわめき、ノイズ、そして沈黙。
場面転換時に無音を挟み、観客の耳を“待機状態”にさせる。
その直後に“鏡が震える音”“ガラスが揺らぐ音”などが挿入される。
このリズムが、恐怖の拍節を作る。
また、映画には“音の逆再生”“ノイズ混入”“録音データの乱れ”といった演出があり、
映像と音が互いに不安定さを補完している。
3. 視点/撮影手法とメタ性
作品内で“撮影”が多用される点が特徴的だ。
ヤヒロはカメラを持って部屋を歩き、録画し、配信を意識する。
この「撮る行為」と「映る行為」が交錯することで、恐怖が観客に跳ね返ってくる。
彼がカメラを向けた先に怪異が現れるだけでなく、カメラ自身が歪む、ノイズが乗る、映像がずれる。
それはまるで、怪異そのものが“撮られること”を拒否しているかのようだ。
このメタ構造は、現代ホラーでよく使われる“スクリーン内スクリーン”の手法だが、今作はそれを「部屋」という最も私的な空間に適用させるところに新味がある。
4. キャラクター演出・心理的揺らぎ
ヤヒロは一見、軽いタッチの芸能人だ。
しかしその“軽さ”と“脆さ”を利用して、恐怖に引き込まれていく過程が丁寧に描かれている。
彼の震え、目線の揺れ、呼吸音の増幅は、演技と演出の境界で機能している。
花鈴の存在感も重要だ。彼女はヤヒロに対して信頼と不安を抱き、恐怖に引きずられながらも最後まで踏みとどまろうとする。
彼女自身の過去やトラウマも示唆され、物語に深みを出している。
また、脇役たち(不動産屋、霊媒師、不動産担当者など)の語りと振る舞いが、“語り手”としての役割を果たす。
彼らが語る事故の噂、物件の履歴、視覚的描写の補助、恐怖の予兆を提示する役割を持つ。
5. 怪異のデザインと揺らぎ
幽霊・気配・手の影・鏡面反射・血痕・黒い影の増殖など、怪異表現は多様だ。
だが、決して“見せすぎない”ことに重きを置いている。
フェードイン・フェードアウト、暗部残像、コントラストの曖昧さ、揺らぎの処理など、
観客の想像力を使わせる余地を残す演出が多い。
特に鏡のシーンは、この映画の肝といえる。
鏡に映るものと実像の差異、鏡に触れた瞬間の歪み、視線の錯覚。
これらが「見えるかもしれない」「見えないかもしれない」という緊張を生む。
第4部 私的読後感 ―― 壁の向こうで祈る誰かの存在
この映画を観た後、私は自室の壁を撫でた。
その壁の厚さの向こう側に、何があるのか――震えるように知りたくなる感覚に囚われた。
最も印象に残ったのは、「恐怖とは他者の物語ではない」という感覚だ。
ヤヒロが“動画ネタ”を求めて事故物件に踏み込む動機は、一方的なものだ。
だが、怪異が彼を受け入れず、むしろ彼の内面を映す鏡となって襲ってくる。
私はこの映画を、“部屋と過去、視線と暴露”のホラーだと感じた。
部屋はただの生活空間ではなく、過去の記憶の鏡、その存在が、住む者を映し出す舞台だ。
また、“撮ること”と“見られること”の関係性を問う映画でもある。
ヤヒロがカメラを構えるとき、その先にあるのは他者か、幽霊か、自分か。
その曖昧さこそが、この映画の怖さを深めている。
少し気になった点もある。
説明的すぎるセリフや演出が、ラスト付近でやや強引に感じられる瞬間がある。
また、全体における恐怖レベルの波が多少揺れ、急にリアルさとファンタジーの境界が崩れる場面もあった。
だが、それらを許せるほど、映画の語るものには重みがある。
恐怖を“見せる”より、“感じさせる”ことを選んだ意志が感じられる。
第5部 総評と星評価
この映画を通して私は知った。
“家”というもっとも親密な空間にも、誰かの足跡と忘却が残るのだと。
国内ホラー映画としての意欲と完成度を持ちつつ、
メディア/視聴行為への問いも含ませた本作は、
単なる“怖がらせ”映画ではなく、複層的なホラー体験を提供する。
以下、私による星評価を付けておく。
| 項目 | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 物語構成 | ★★★★☆ | 怪異と過去、メディア意識を絡めた構成は巧み。だが終盤説明過多感も若干。 |
| 演出・映像 | ★★★★★ | 空間の歪み、間取りのズレ、鏡・影の演出など映像的強度が高い。 |
| 音響・演出効果 | ★★★★★ | 静寂とノイズの対比、暗転・逆再生などサウンドで恐怖を刻む演出が秀逸。 |
| 俳優・心理表現 | ★★★★☆ | 渡辺翔太、畑芽育らの内面表現にリアリティあり。もう少し掘り下げが欲しかった面も。 |
| テーマ性・余韻 | ★★★★★ | 撮る/見られる、家と記憶、過去との共振などのテーマが心に残る。 |
▶ 総合評価:★★★★☆(4.5/5)
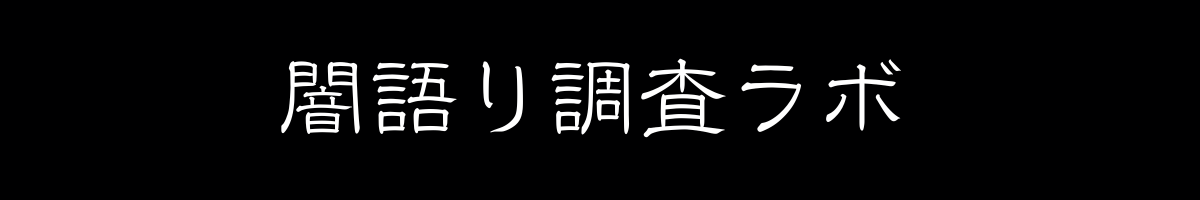




コメント